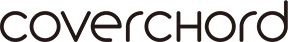COVERCHORD FEATURE
来民渋うちわ・栗川商店
涼と縁起を呼び込む、伝統のうちわ
実用の道具としても、美しいインテリアとしても。
130年の歴史を誇る、熊本県・来民で作られる伝統のうちわ。

京都うちわ、丸亀うちわと肩を並べる熊本県山鹿市の伝統工芸「来民渋うちわ(くたみしぶうちわ)」。
1889年創業の〈栗川商店〉は、現在この「来民渋うちわ」を製作する唯一の工房である。
職人の手によって一本一本丁寧に仕上げられる「来民渋うちわ」は、単なる道具ではなく、歴史と技が息づく逸品だ。
わずかな扇ぎでも心地よい涼風を生み出す、風をよくつかむ造形が特徴。
真竹と和紙で形を作り、さらに柿渋を塗布することで和紙を丈夫に保つと同時に、タンニンの働きによって防虫効果の役目を果たす。淡い茶色が時間の経過とともに次第に深みを増し、味わい深い美しい茶色に変化を見せる。
涼を取る道具としてはもちろん、食材を冷ます実用的な調理道具として、さらには、その美しいデザインから空間を彩るインテリアとしても人気を集めている。
「民が来る」という意味から、商売繁盛の縁起物とされ、大切な人への贈答品としても最適だ。
今回COVERCHORDは、熊本県山鹿市にある〈栗川商店〉の工房を訪れ、その製作工程を取材した。
伝統工芸・来民渋うちわとは
「来民渋うちわ」の起源は、慶長5年(1600年)にさかのぼる。
香川県・丸亀から訪れた旅の僧が、一宿のお礼としてうちわの製法を伝えたことに始まったとされている。
山鹿は、古くから楮(こうぞ)の産地として知られ、和紙づくりが盛んな土地であった。さらに、阿蘇外輪山にはうちわの骨に適した真竹が豊富に自生しており、うちわ作りに理想的な環境が整っていた。
そのため、うちわ作りの技術は地域に根づき、江戸時代には肥後熊本藩・細川家の後押しを受け、伝統手工業として発展していった。うちわ作りは受け継がれ、昭和初期に最盛期を迎える。
最盛期の山鹿には35軒のうちわ製造業者が軒を連ね、年間600万本ものうちわが作られていたという。
「来民渋うちわ」は、大きく分けて5つの工程を経て完成する。
中でも、その最大の特徴は最後の仕上げに行われる「渋塗り」と呼ばれる工程である。
青く未熟な「がら柿(豆柿)」から採れる柿渋を塗ることで、防虫・防腐・防水といった効果が加わり、丈夫で長持ちするうちわになる。
使い込むうちに色味が深まり、味わいを増していくのも、「来民渋うちわ」ならではの魅力である。
物を売る時代から、心を伝える時代へ
栗川商店
1889年の創業以来、130年以上に渡り「来民渋うちわ」の製造と販売を行ってきた〈栗川商店〉。現在では、日本で唯一「来民渋うちわ」を手がける工房である。
先代の栗川亮一氏が家業を継いだ1991年当時、うちわの主流はすでに広告用のプラスチック製へと移り変わっていた。
伝統的なうちわの需要は大きく落ち込み、かつて当たり前に受け継がれてきた技術も、時代の変化とともに次第に廃れつつあった。
そうした中、栗川氏は「来民渋うちわ」が持つ素朴さと風合いに改めて価値を見出し、記念品や命名うちわといった贈答用としての可能性に着目。
伝統の製法を守りながらも用途を広げることで、新たな展開へと舵を切った。
先代から受け継いだ技術と精神を礎に、現代の暮らしにも寄り添う“美しい道具”として、〈栗川商店〉の「来民渋うちわ」は多くの人の心をとらえ、今では年間3万本を製作するまでに成長している。
現在、工房を率いるのは5代目当主の栗川恭平氏。
長い歴史を受け継ぎながら、「物を売る時代から、心を伝える時代へ」という先代の言葉を胸に、心を込めた作った伝統の「来民渋うちわ」を、国内外問わず多くの人々に届け続けている。

5代目当主・栗川恭平氏
工房を訪ねて
来民渋うちわ ができるまで
〈栗川商店〉の「来民渋うちわ」作りは、「骨割り」、「貼り」、「形切り」、「補強」、「渋塗り」、五つの主要工程を経て完成する。
現在〈栗川商店〉にはおよそ10名の職人が在籍しており、それぞれの工程を専門職人が手掛ける、完全分業制を採っている。
同時に、NPO法人「伝承塾」を立ち上げ、山鹿市およびその周辺地域に暮らす心身に障がいのある人々を作り手として受け入れ、伝統工芸の技術を身につけることによる自立の支援にも取り組んでいる。
カレンダーや名刺、タオル印刷、日用品の卸売のほか、うちわ作り教室など、多岐に渡る事業も展開しながら、1日に100~200本、年間で約3万本の「来民渋うちわ」を製造・販売している。
今回COVERCHORDは実際に工房を訪ね、「来民渋うちわ」ができるまでの製造工程を見せていただいた。
骨割り
うちわの礎となる骨組みを作る工程。
素材となる真竹は阿蘇外輪山産を中心に、直径7寸以上・3年物を調達し、加工しやすいよう2~3日水につけ柔らかくする。
細く割り、先端をさらに細かく裂いて放射状に広げ、加工を施す。

割き機(わきき)と鉈(なた)を使い、
割った真竹の先をさらに細かく割る。
1本あたり0.4~0.5mmの薄さにした竹を手でひねり、
繊維をほぐし、放射線状に広げる。
横穴をあけ、竹棒を通し、持ち手を研磨し、
糸で編み、ようやく骨組みの完成。
しっかり天日干しをして次の工程へ。
貼り
骨組みに和紙を貼り付ける工程。
昔は地元の和紙を使っていたが、現在では八女手漉和紙を中心に、県内外のものを使い分けている。
和紙の繊維方向を見極めながら、でんぷん糊で骨組み両面に貼る。


形切り
和紙と骨組みの余分な部分を切り落とす工程。
丁寧に形切り包丁(なりきりぼうちょう)をあてがい、槌で打ち付けることで、一瞬でうちわの形が完成する。

恭平氏が兄弟子から受け継いだ槌。
使用する職人によって打ち方が違うため
上は兄弟子、下は恭平氏、それぞれによる凹み。
補強
「形切り」で断った箇所が破れやすいので、うちわの縁と根元の部分に、細く切った和紙を貼る。
縁取り(へりとり)とも呼ばれる工程。

渋塗り
「来民渋うちわ」最大の特徴である仕上げの工程。
柿渋を塗ることで、防虫・防腐・防水といった効果が加わり、丈夫で長持ちするうちわになる。
〈栗川商店〉では創業以来、山鹿産の未熟なガラ柿(豆柿)から自家製の柿渋を仕込み、3年以上発酵・熟成させたものだけを使用している。
毎年8月初旬に仕込みを行い、
搾った生渋を自然発酵させて熟成させる。
これにより、使うほどに味わいが増す
「来民渋うちわ」が生み出される。

柿渋を手早く均等に塗布し、
日陰で乾燥させて仕上げる。

栗川商店の
来民渋うちわ

仏扇 柄
Price_¥1,500
Size_L 30cm W 14.5cm

仏扇 無地
Price_¥1,200
Size_L 30cm W 14.5cm

仙扇 無地
Price_¥2,500
Size_L 37cm W 25cm

小丸 無地
Price_¥1,700
Size_L 38cm W 19cm

小判 無地
Price_¥2,500
Size_L 37.5cm W 18cm