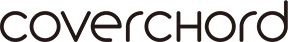COVERCHORD EXCLUSIVE
ハラダマホ 個展
at COVERCHORD
“練り上げ”のうつわ
繊細で緻密な“練り上げ”技法によって生み出される、
やわらかい色彩と個性的な幾何学模様のうつわ。初となる個展を開催。
5月17日 (土) 発売
優しい色彩と幾何学模様が織りなす、唯一無二の“練り上げ”のうつわ。
熊本県・山都町にて制作活動を続ける陶芸家〈ハラダマホ〉さんの個展を、COVERCHORD Nakameguro、Fukuoka 両店舗にて、6月7日 (土)より開催します。
〈ハラダマホ〉の作品には、“練り上げ”と呼ばれる高度な技法が用いられています。
色粘土を組み合わせて模様を作り、型にあてて成形することで、うつわの内部にまで模様が貫かれるのが特徴。
ユニークなデザインと独特な色彩が目を引く作品たちは、どれも気が遠くなるような長い時間と、緻密な作業を経て生み出された一点ものです。
COVERCHORDでは初となる個展に向けて制作された作品には、ハラダさんが日々の生活の中で感じた心の機微がデザインや色彩となって投影されています。
うつわに宿った、心情や人のぬくもり。ぜひお手に取ってお楽しみください。

雄大な自然に抱かれた
工房を訪ねて
〈ハラダマホ〉の作品を初めて目にする方は、その繊細な色彩模様を、絵付けによるものと見紛うかもしれません。
しかし実際は、数ある陶芸技法の中でもとりわけ緻密で時間のかかる“練り上げ”と呼ばれる手法によって生み出されたものです。
“練り上げ”技法の工程は多く、原料からひとつのうつわが生まれるには、最低でも3ヶ月から6ヶ月を要します。制作作業の前にはイメージを図案に落とし込む構想期間も必要で、もちろん大量に制作できるものではありません。
それぞれに顔料を練り込んだ様々な色粘土を捏ね、デザインした図案を元に幾何学模様を形づくり、それをスライスして石膏型にあてて成形してゆきます。
時間と手間をかけて、一つひとつ丁寧に作られています。
色を組み合わせた粘土のどこを切っても同じ模様が現れる様は、まるで金太郎飴のようです。
釉薬による表面への着色ではなく、原料そのものに色をつけることで、深みとやわらかさをあわせ持った独特の色彩を宿すうつわが生まれます。
しかし、“練り上げ”技法は非常に難しく、色ごとの収縮率や粘りの違いからひび割れが生じやすく、歩留まりも極めて低いと言われます。
それでもハラダさんは、“練り上げ”でしかなし得ない表現に魅せられて、真正面から制作に向き合い、長い試行錯誤の末に、唯一無二のスタイルを確立しました。
〈ハラダマホ〉のクリエイションの一端を知るべく、COVERCHORDは熊本県・山都町の静かな山あいにある彼女の工房を訪ねました。
熊本空港から車で約40分。山あいの道を進んだ先、人里はなれた場所に、ハラダさんの制作拠点があります。作陶の合間には、ご両親の農作業を手伝いながら過ごす日々。
窓の外には、四季折々に美しい表情を見せる棚田が広がり、その向こうには雄大な山々の稜線。自然に抱かれた、静かで豊かな場所です。
今回は特別に、練り上げ工程のうち「成形」作業を見せていただきました。
はじめに、色と模様を組み合わせた土を組むのに1ヶ月を要し、さらに3ヶ月寝かせたものを、「たたら板」を使って狙った厚みに手早くスライスしていきます。
「技術も必要ですが、とにかく養生が大事なんです。色土の混入やキレの原因になる急乾燥を防ぐことに気を遣います」
土をはじめ原料はすべて自然由来。環境や湿度・温度にも左右され、同じ色でも毎回違いが生まれます。
「経験を積むことで定番の型は安定してきましたが、新しい柄は10枚成形して1枚しか完成まで残らないことも。ベストを尽くしても、最終的には運のようなものもあります」
5mm幅にスライスされた土は水分が均一になるまで1日寝かせ、型に合わせて細かく形を整えます。
うつわの石膏型に合わせ、優しく包み込むように土を押し当てて、成形してゆきます。
底の部分は柄がぎゅっと絞られる繊細な箇所。模様が崩れないよう余分な土を切り落としながら、丁寧に馴染ませていきます。
「実は、独立してから初めて、手探りで成形を始めたんです。習うことではないので、“練り上げ”について他の人がどうやっているかも知らないし、まだまだペーペーです(笑)」
鮮やかな手つきでうつわの形をつくりながら、そんな驚きの言葉がこぼれました。
佐賀県の有田窯業大学校で焼き物の基礎を学び、在学中に出会った“練り上げ”の魅力に惹かれて、卒業後は山梨県の「會田雄亮研究所」へ。
そこでは成形技術を直接学ぶことはなく、ひたすら土を練りながら、陶芸歴30年の技を目で見て覚えたといいます。
「どこもそうだと思いますが、1から10まで教えてもらえるほど、ものづくりの世界に時間の猶予はないのかなって」
確立された方法を教わるのではなく、自分の手と感覚で積み重ねてきた道のり。試行錯誤の先に生まれた一つひとつのうつわには、ハラダさんの今までの歩みと静かな確信が刻まれています。
ご実家のほど近くにある農作業小屋の一角を、自ら手を加えて工房に仕立てたというハラダさん。清潔に保たれた空間には、随所に彼女の心地よいセンスが光り、どこか静謐な空気が漂います。
作業が始まると雰囲気が一変し、空間にはぴんと張り詰めた緊張感が生まれます。
「愛犬の金之助がよく工房にいるんですが、私が成形している時は一声も発さないんです(笑)。ものづくりをしている人って、たぶん結構険しい顔してるんでしょうね」
少し照れくさそうに笑いながら、こんな一言も。
「鶴の恩返しも、見られたら百年の恋も冷めちゃうって思ったのかも」

軽く叩いて形と柄を馴染ませたあと、余分な土を丁寧に切り落とします。
石膏型を外した後も、水分を含ませながら、緻密で繊細な手仕事が続きます。
「ここで時間をかけて丁寧に仕上げるかどうかで、次の工程へ行けるかが決まります。たとえ切れてしまっても、やれるだけのことをやったと思えれば納得できる。でも、あのときちゃんとやっておけば……って後悔するのは嫌なんです。
年々、そういう見えない作業に時間がかかるようになっているかも。長くやればもっとたくさん作れるようになると思っていたけど、全然そんなことなかったですね(笑)。むしろ減ってるかもしれません(笑)」
その言葉には、静かな決意と、ものづくり真摯に向き合ってきた時間の重みが滲んでいました。

イメージの源流と、
方眼紙から始まる物語
ハラダさんのうつわ作りは、いつも一枚の方眼紙から始まります。
頭に浮かんだイメージを、幾何学模様に整え、丁寧に図案へと落とし込んでいく。
「方眼紙が昔から好きで。なので作業の中でも図案を書くのが一番好きなんです。ずっと続けていることって、あんまり変わらないですね」
ものづくりに携わりたいと入学した窯業の専門学校時代。友人に連れられて入った有田のお店で見た、ひとつのうつわ。それが“練り上げ”との出会いでした。
中まで模様が入り込んだそのうつわからは、どこか圧のようなものを感じたといいます。
そこから始まった“練り上げ”の道。今では、生み出した模様一つひとつに、名前がつけられています。

図案を構想する際、配色のパターンを確かめるための、色粘土サンプル。
楕円皿 - in the pool ¥36,000
中皿 - GO! ¥17,000
「最初は、柄が増えすぎて電話で説明するのが大変になって(笑)。それで伝わりやすいようにと名前をつけはじめたら、お客さんでも面白がってくれる人が増えてきました。」
インスピレーションの種は、日常のあちこちに転がっています。
作業中に流れるラジオや、レコードの音楽、雑誌のフレーズ。普段の何気ない会話にもアンテナを張っているといいます。
タイトルを絞り出すこともあれば、先行してタイトルがすんなりと浮かぶことも。
「その言葉についてずっと考えていたら、だんだんそのイメージが形になってくる。方眼紙の前に座って、手が動いてるんです」
明確な意図があるというよりは、ふと気になった言葉や風景が、形へと結晶していくような感覚。
工房の随所に、彼女の心地よいセンスや遊び心が光る。
丸皿 - ワラビとゼンマイ ¥36,000
ラッパカップ - 地球は回る ¥9,500
今回の個展に出品されるうつわは、自然の中のモチーフが多く形になっていました。
あとから作品を眺めて、制作していた時の自分の心の状態に気づかされることもあるといいます。
「ぼんやりしていても、気になることってあるんです。意識していなくても、ずっと残っているものって、やっぱりどこかに流れ込んでいるんですよね。」
そうやって形になっていく、日々の小さな気づきや感覚の断片。それが今も変わらず、彼女のうつわを形づくっているのかもしれません。
「飽きずに、楽しくやっていけていることがとにかくありがたいですね」

カップ&ソーサー - 日光浴 ¥20,000

ハラダマホ 個展
at COVERCHORD
会期:2025年6月7日(土) – 11日(水) 11:00 - 19:00
※お一人様4点までの購入制限を設けさせていただきます
※会期中、COVERCHORD Online での販売はございません
会場:COVERCHORD Nakameguro
東京都目黒区青葉台1-23-14
Instagram_@coverchord nakameguro
会場:COVERCHORD Fukuoka
福岡県福岡市中央区警固2-17-23 1F
Instagram_@coverchord_fukuoka

ハラダマホ
1977年 熊本生まれ。
1999年 佐賀県立有田窯業大学校卒業。會田雄亮研究所入社。
2001年 熊本にて設窯。
個展によせて -作家コメント-
窯の表記を見ると2001年8月設置とありました。
なんともはや24年が経とうとしています。
しぶとく続けてきたのは、見えない部分にも模様を組み込む練り上げ技法、
その熱量の高さに今も心惹かれているからだと思います。
COVERCHORDに展示された作品が見る方の心揺さぶり
何か語りたくなるような心持ちにさせるのなら幸いです。